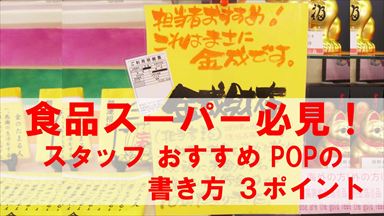経営理念に共感して入社した私が見た理念浸透の仕組み
13年間務めた会社を退職した私は働くことの意味に迷っていました。
それなりに頑張っていたとは思うのだけれど、何だか空回りして、何のために一生懸命やっているのか実感できなかったのです。
求職活動は2つの選択肢で考えていました。
一つは前職の経験を活かした仕事に応募すること。
もう一つはある経営理念の会社に応募すること。
募集はしていませんでしたが、その会社に履歴書を送らせていただき入社しました。
そして入社後に受けた経営理念にふさわしい新人教育。
社会に出てからの16年間に学んでわからなかったこと、その間に生じた様々な疑問に全て答えのあるものでした。
お客様を中心としながら、自身もイキイキとして働く
何のために働くのか、何のために生きるのかを実感として感じる日々
そこからの16年間は私の人生で最も輝く期間となりました。
このメッセージでは、私が経営理念に共感して入社した会社で見た「経営理念が浸透する仕組みと背景にある思い」を、具体的な体験を交えてお伝えします。
経営理念を「伝えるだけ」で終わらせず、「活きたものにしたい」と考える経営者の方に、きっとヒントになるはずです。
目次
私が共感した経営理念との衝撃的な出会い
全く知らない業種なのに、なぜその会社に応募したのかというと、経営理念が記憶にあったからです。
その経営理念との出会いは次のようなものでした。
同じ経営コンサルタント会社の担当者のこ゚縁で、業種の全く違う会社の朝礼を見学させていただいたことがありました。
その朝礼は社長と社長室長と従業員5~6人が売場で輪となって、主任の司会で行われました。
全員での経営理念の唱和から始まりました。
「顧客中心の店づくりをする」から始まる4か条
(実際の経営理念とは表現が少し違います)
その後、社長のコメントや連絡事項、各担当からの発言があったように思います。
その経営理念は私にとっては本当に衝撃的でした。
「なんて羨ましい!そんな誇らしい思いで仕事ができるなんて」
どんなに大変な仕事でも、顧客のため、社会に役立つためという目的
どれだけ頑張っても報われる根拠がある風土
仕事に意味を与える経営理念
その朝礼の見学で覚えていたことといえば、その経営理念のことしかありませんでした。
自社の朝礼の改善や経営理念の浸透などに参考になったかというと、全く違う業界だったせいか、それ以上の進展はありませんでした。
それでも
共感したその経営理念は私の頭からずっと離れることはありませんでした。
数年後、会社を退職することになりました。
何を根拠に求職活動をするのか?
何のために働くのか?
前職の経験を活かした仕事に応募する・・・それで何が変わる?
記憶にあったのはあの経営理念でした。
全く知らない業界でやっていけるのか?
不安でしたが、朝礼を見学したときに共感した経営理念が頭にありました。
募集はしていませんでしたが、その会社に履歴書を送らせていただきました。
幸いなことに新規出店の準備を進めていたこともあり、採用となりました。
そして入社後に受けた新人教育。
共感した経営理念にふさわしい新人教育でした。
単なるきれいごとではなく、実際の現場で「活きた理念」
日を追うごとに、私はその経営理念にさらに強く共感しました。
この会社で働くことに迷いがなくなるどころか、誇りを感じるようになりました。
そこから16年間は私の人生で最も輝く期間となりました。
経営理念を浸透させる原点は新人研修にあった
入社初日、私の研修は社長と社長室長が担当された研修項目は印象的でした。
中途採用だった私は新人研修を受けるのは私一人、研修の担当(トレーナー)は社長と社長室長の二人、社長室で面と向かっての研修でした。
お二人が私一人だけの新人研修に貴重な時間を使って経営理念を説明しているのは並々ならない力の入れようだということが伝わってきました。
それだけでも、この新人研修が重要だということが伝わると思います。
講師の社長、社長室長も真剣そのものですから、私も真剣にならざるを得ません。
驚いたのは
最初の1時間を丸ごと使って社長が経営理念について自分の言葉で理念の意味と想いを語ったことです。
「経営理念は飾りではない。私たちの行動の基準であり、判断の軸です」
その熱意に、私は経営理念に共感して入社したことに間違いはなかったと確信しました。
社長の説明する新人研修の重要部分には社長自らが手書きした「FM(Fresh man)手帳」という資料がありました。
手書きですから、ワープロ文書と違って想いが伝わります。
単なるマニュアルではなく、社長の経営理念に対する思いが書かれています。
資料は
「行動目標(3項目)」
「5つのサービス(接客5つのサービス、商品5つのサービス、仲間5つのサービス)」
「5W2Hメモ」
「スターティング5」
「Gチェック7か条」
「商品ベスト10か条」など
韻を踏んだ覚えやすい表現や、箇条書きで要点を整理した項目が並んでいます。
たとえば以下のようなフレーズです。
行動目標
・シンプル:単純明快がよい、複雑怪奇は続かない
・パワフル:力強く熱意を持ってやる
・キーピング:なにごとも続けなくては意味がない
これらは単なるスローガンではなく、
実際の現場で社員が判断に迷ったときの「心の指針」となるものでした。
さらに
この研修資料は定期的に改訂され、その度に全社員に配布されます。
改訂部分をミーティングで再確認し、従業員全員が学び直す文化が根づいています。
経営理念の説明後に唱和も社長自ら、見本を見せていただき、一緒に2回唱和しました。
「明日本店の朝礼で経営理念を唱和するリード役をお願いしたいので、経営理念を唱和できるように覚えてきてください」
これが新人研修1日目の宿題でした。
このことからもわかるように、この会社では今日入社の新人も含め、全員が経営理念を唱和するのです。
最も社長から遠い存在で、最も社歴の浅い人でも経営理念を唱和できるか?
経営理念が浸透しているかいないかを測る目安の一つだと思っています。
翌日の本店での朝礼では経営理念唱和のリード役を仰せつかり、経営理念を唱えたのですが、途中ちょっとつかえてしまいました。
全員での経営理念の唱和が終わり、参加者全員が拍手してくれました。
ちょっと照れくさい感じがしましたが、何だか同じ会社の仲間になれたような気がしたのを覚えています。
新人研修1日目は①~⑥までを社長が担当、⑦~⑭を社長室長が担当されました。
① FM(新人)の心構え、
② 経営理念、行動目標と組織、
③ 会社の歴史と計画、
④ 当社の特徴、
⑤ 年度方針
⑥ 5つのサービス(接客、商品、仲間)
⑦ この業界の説明
⑧ 就業規則
⑨ 勤務体制
⑩ 給料
⑪ 社会保険
⑫ 社員預金、社内融資、社内販売
⑬ 5W2Hメモ
⑭ 身だしなみ
2日目以降の新人研修は各店舗の店長や主任がトレーナーとして担当されました。
新人研修は全部で56項目、1週間くらいかかり、更に1週間後には確認テストもありました。
店長が理念浸透のキーパーソンだった
理念の浸透は、社長だけでなく「店長という現場リーダー」によっても支えられていました。
私の新人研修初日は社長と社長室長がトレーナーとして担当するという特殊なケースでした。
通常、新人研修は社長、店長、幹部によって行われます。
新人研修の①~⑥項目までは主に社長または店長が担当し、それ以降の項目は店長、幹部が行います。
① FM(新人)の心構え、
② 経営理念、行動目標と組織、
③ 会社の歴史と計画、
④ 当社の特徴、
⑤ 年度方針
⑥ 5つのサービス(接客、商品、仲間)
社長が担当する場合には必ず店長が同席します。
社長の説明する経営理念は話すポイントや強調することは毎回少し違います。
店長は①~⑥項目の経営理念や行動目標などは新人と一緒に数十回、店長によっては数百回を超えて聞くことになります。
なので
店長は社長の代わりに経営理念や行動目標などを同じような熱意で意味や想いを話すことができるのです。
そして
店長は新人研修での説明だけではなく、現場ではお客様とのやり取りの中で理念を体現する役割も担っています。
店長は経営理念を浸透させ、体現するキーパーソンなのです。
理念を日常に溶け込ませる「唱和」の文化
理念の浸透を支えていたもう一つの柱が「唱和」です。
入社して2日目には、本店の全員が集まる朝礼で、私も経営理念を大きな声で唱和のリードをしました。
最初は少し恥ずかしさもありましたが、次第にその意味を理解しました。
理念を「声に出す」ことで、「頭で理解していた言葉が心に刻まれていく」のです。
新入社員の中には唱和を好まずに辞めていく人もいましたが、私はとても誇らしく思います。
この会社では、朝礼や会議など、あらゆる場面で経営理念を唱和します。
特に年に一回の年度方針発表会での全社員による唱和は毎回、感動さえ感じました。
店長もパート社員も、全員が同じ理念を口にする。
毎日のように繰り返すことで、理念が自然と行動の中に染み込んでいきます。
ある時、店長がこう言いました。
「理念を唱和するのは、単なる儀式じゃない。
私たちが毎日初心に戻って、顧客中心主義を確認するためなんだ」
その言葉の通り、唱和は形ではなく「心を整える時間」になっていました。
経営理念は「変わらないもの」ではなく「進化するもの」
この会社に勤めている間、私は「2度の経営理念の変更」を経験しました。
最初は驚きました。
「理念って変わるものなの?」と戸惑いもありました。
しかし社長はこう説明しました。
「理念は守るものではなく、磨き続けるもの。
会社が成長し、環境が変わる中で、より今の経営方針に合う形に進化させていく必要がある。」
確かに、その変更は単なる言葉の置き換えではありませんでした。
新しい理念は、時代の変化に合わせて会社の新しい目標をより明確にするものでした。
そして
驚くことに、その変更を通じても「会社の軸は全くブレなかった」のです。
むしろ理念を再定義することで、社員の意識はより全社一丸となりました。
理念が「活きている」からこそ、環境の変化に合わせて「変わる」。
この経験を通して
私は、理念は「固定した看板」ではなく、「成長し続ける心」なのだと実感しました。
変化しても揺るがない「理念の核」とは
理念が変わっても、そこに流れる「核」は変わりませんでした。
それはお客様中心主義という精神です。
言葉の表現は少しずつ変化しても、この価値観だけは一貫して守られていました。
理念が変わっても混乱が起きなかったのは、社員全員がその「核」を理解し、自身の想いとなっていたからです。
社長も店長も、理念変更のたびに丁寧に説明し、全員で新しい理念を唱和し直しました。
「理念は変わるが、想いは変わらない」——この姿勢が、会社全体に安心感と一体感をもたらしていました。
理念が進化するたびに、社員も自分の仕事の意味を再確認する。
「経営理念が、組織と人、企業文化を育て続けている」ことを感じた瞬間でした。
まとめ:経営理念が共感され、浸透し続ける会社の条件
私がこの会社で学んだのは、経営理念とは「つくって終わり」ではないということです。
理念は掲げるだけでは浸透しません。
- 社長が自身の言葉で熱く語り続けること
- 店長というキーパーソンが現場で体現すること
- 社員全員が毎日唱和し、自身の心と行動に落とし込むこと
この三位一体の仕組みこそが、理念を「共感される言葉」から「生きた文化」へと育てていました。
そして何より印象的だったのは、理念が変化したときの会社の姿勢です。
経営方針や時代の変化に合わせて理念を進化させる柔軟さこそ、「活きた理念を持つ会社の証」なのだと感じました。
経営理念は変わらないものではなく、「変わりながら生き続けるもの」。
私が共感して入社した会社は、そのことを実践で教えてくれました。
経営理念の浸透にはプロフィールのエピソードも参考になると思います。